|
|
| 【アーカイブ配信】をご希望の方はこちらをクリックしてください |
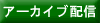
|
|
| <セミナー No508115 (Live配信)、509162(アーカイブ配信)> |
|
|
| |
|
・有効成分や用途、製造方法に関する特許調査の実務と、その検索式作成のコツがわかる!
・侵害調査、配列情報の検索にも対応し、最適なサーチ戦略構築に役立つ実践知が得られる!
|
〜実演で学ぶ〜
医薬品特許調査の効率的手法と
その検索式事例
|
|
| ■ 講師 |
|
青山特許事務所 東京オフィス 顧問 弁理士、知的財産大学院協議会 会長 加藤
浩 氏
|
|
| ■ 開催要領 |
| 日 時 |
: |
2025年8月29日(金) 10:00〜16:00
【アーカイブ(録画)配信】
2025年9月9日(火)まで申込み受付(視聴期間:9/9〜9/19)
|
| 会 場 |
: |
Zoomを利用したLive配信 or アーカイブ配信いずれか ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
|
| 聴講料 |
: |
聴講料 1名につき55,000円(消費税込/資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕
〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくは上部の「アカデミック価格」をご覧下さい〕
|
|
| ■ プログラム |
|
【講座主旨】
近年、医薬品分野では、研究開発の高度化に伴い、研究成果が積極的に特許出願され、特許実務が重要視されています。このような状況の下、医薬品に関する特許調査の重要性が高まっています。
医薬品の特許調査を適切に行うことは、広くて強い特許の取得だけでなく、研究開発の推進にとっても重要であり、研究開発戦略や特許戦略の向上にもつながります。このような特許調査を的確に行うためには、技術水準や技術動向をしっかりと認識し、特許要件や侵害の範囲に配慮し、外国特許を含めたグロ−バルな特許調査を行うことが重要です。
また、近年、人工知能(AI)の利用が普及する中、人工知能を利用した特許調査についても普及しつつあります。今後とも、より精度の高い特許調査への期待が高まることから、人工知能を利用した特許調査の導入が企業戦略にとって必要不可欠です。
本講演では、医薬品の特許調査の基礎と実践として、的確な特許調査の手法について解説します。また、有効成分、医薬用途、用法・用量、製造方法など、特定テーマごとの特許調査についても説明し、特許調査の実演を行うことにより、最適なサーチ戦略の構築に向けた有益な知見を提供します。
【講座内容】
1 特許調査の基本と実務
1-1 先行技術調査の進め方
1-2 国内特許と外国特許のサーチ手法
1-3 技術水準や技術動向に配慮した調査手法
1-4 特許要件に配慮した調査の必要性
2.有効成分に関する特許調査
2-1 低分子化合物
2-2 中分子化合物(核酸、ペプチド)
2-3 抗体、蛋白質
2-4 微生物(再生医療、細胞治療)
3.医薬用途に関する特許調査
3-1 用途発明における発明の認定
3-2 用途に関する検索式の作成方法
3-3 特許分類(A61P)の利用方法
3-4 医薬用途の作用機序への配慮など
4.用法・用量、製造方法に関する特許調査
4-1 用法・用量における発明の認定
4-2 用法・用量に関する検索式の作成方法
4-3 製造方法に関する検索式の作成方法
4-4 実施例レベルの開示情報の調査手法)
5.生物材料 (細胞・微生物) に関する特許調査
5-1 生物材料における発明の認定
5-2 細胞・微生物に関する検索式の作成方法
5-3 特許分類(C12N)の利用方法
5-4 再生医療、細胞治療のクレームの特徴
6.アミノ酸配列・塩基配列に関する特許調査
6-1 アミノ酸配列・塩基配列における発明の認定
6-2 アミノ酸配列・塩基配列に関する検索式の作成方法
6-3 特許分類(ZNA、その他)の利用方法
6-4 配列表、配列番号に配慮した調査方法
7.特許侵害調査の実務
7-1 特許侵害調査とクリアランス調査
7-2 侵害の範囲に配慮した特許調査
7-3 最近の裁判例を考慮した調査手法
7-4 特許マップの作成と活用方法
8.特許調査の実演
8-1 低分子医薬
8-2 中分子医薬(核酸医薬、ペプチド医薬)
8-3 抗体医薬、蛋白質医薬
8-4 再生医療、細胞治療
8-5 最適なサーチ戦略の構築に向けて
【質疑応答】
|
|
