| |
| 【アーカイブ配信】をご希望の方はこちらをクリックしてください |
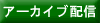
|
|
|
<セミナー No 512236>
|
|
|
|
★ 官能基密度、分子量、柔軟鎖導入量などの最適設計のヒントが得られる!
★ 架橋反応の制御へ! DSCによる反応熱解析、IRによるエポキシ量の分析!
|
|
エポキシ樹脂のフィルム化と
接着性の向上、分析・評価
|
|
| ■ 講師 |
|
溶解技術(株) 代表取締役 博士(工学) 柴田 勝司
氏 |
|
| ■ 開催要領 |
| 日 時 |
: |
【Live配信】2025年12月23日(火) 10:30〜16:30
【アーカイブ(録画)配信】 2026年1月8日まで受付(視聴期間:1月8日〜1月18日まで)
|
| 会 場 |
: |
Zoomを利用した Live配信 または アーカイブ配信 ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
|
| 聴講料 |
: |
1名につき
55,000円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕
〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくは上部の「アカデミック価格」をご覧下さい〕
|
|
| ■ プログラム |
【習得できる知識】
・エポキシ樹脂の基礎知識
・エポキシ樹脂を原料とするフィルムの合成と物性
・マスクイソシアナートを用いたエポキシフィルムの架橋
【講座の趣旨】
エポキシ樹脂はこれまで主流であった土木建築、接着剤、電気絶縁材などの用途に加えて、自動車用、航空機用などにも用途が広がり、世界での生産量も拡大している。
本セミナーでは、これらの新分野へ展開できる可能性のある技術として、エポキシ樹脂のフィルム化技術について解説する。現状ではベンゼン環と水酸基を併せ持ち、十分なフィルム形成能を有する高分子は少ない。ベンゼン環によって耐熱性、機械的性質などに優れ、水酸基によって接着性、熱硬化性などが付与できる。フィルム形成後の三次元架橋反応についても詳述する。これに接着性を付与すれば、プリント配線板の基材として利用できるほか、様々な電子材料に利用できると考えられる。また、水酸基を極性の異なる化合物で修飾できれば、耐熱性、耐溶剤性を有する分離膜などにも利用できると考える。また、エポキシ樹脂について豊富な知識をお持ちでない方にもご理解いただけるように、前半ではエポキシ樹脂の基礎知識として硬化剤、硬化促進剤、分析法、評価法についても説明する。
1.緒言
1.1 エポキシ樹脂の定義
1.2 エポキシ樹脂の歴史
1.3 世界の需要
1.4 他の樹脂系との比較
1.5 エポキシ樹脂の特徴
1.6 エポキシ樹脂配合の特殊性
2.エポキシ樹脂の基礎
2.1 エポキシ樹脂
2.1.1 汎用エポキシ樹脂
2.1.2 特殊エポキシ樹脂
2.2 硬化剤
2.2.1 アミン系
2.2.2 酸無水物系
2.2.3 フェノール系
2.2.4 ポリチオール系
2.2.5 潜在性硬化剤
2.3 硬化促進剤
2.3.1 硬化剤と硬化促進剤の違い
2.3.2 アミン系
2.3.3 イミダゾール系
2.3.4 リン系
2.3.5 紫外線(UV)硬化用
2.4 分析法、評価法
2.4.1 赤外分光法 (IR)
2.4.2 核磁気共鳴法 (NMR)
2.4.3 高速液体クロマトグラフィ (HLC)
2.4.4 ゲル浸透クロマトグラフィ (GPC)
2.4.5 示差走査熱量計 (DSC)
2.4.6 粘弾性解析 (VEA)
2.4.7 熱分解ガスクロマトグラフィ質量分析 (Py-GC-MS)
2.4.8 機械的性質
2.4.9 電気的性質
2.4.10 耐燃性
3.エポキシ樹脂のフィルム化
3.1 概要
3.1.1 エポキシ系フィルムの利点
3.1.2 熱硬化性エポキシフィルムの設計
3.1.3 エポキシ重合体の基本特許
3.1.4 二段法による合成
3.1.5 溶媒中での二段法による合成
3.2 エポキシ重合体の合成 ? エポキシ樹脂の選択
3.2.1 共重合モノマーの選択
3.2.2 溶媒種類
3.2.3 触媒種類
3.2.4 各種フェノール類
3.3 エポキシフィルムの物性
3.3.1 粘度
3.3.2 分子量
3.3.3 引張試験
3.4 架橋エポキシフィルム
3.4.1 架橋剤 ? エポキシ樹脂
3.4.2 架橋剤 ? シラン化合物
3.4.3 架橋剤 ? カルボン酸
3.4.4 架橋剤 ? イソシアナート類
3.4.5 イソシアナートのマスク化
3.4.6 引張試験
3.4.7 耐熱性
3.4.8 耐溶剤性
3.5 エポキシ接着フィルム
3.5.1 層間接着フィルム
3.5.2 プリプレグとの比較
3.5.3 架橋剤配合量とTg
3.5.4 接着性の付与
3.5.5 配合設計概念図
3.5.6 接着フィルムの特性
4.結言
4.1 結論
4.2 今後の課題
5.質疑応答
|
|
|
